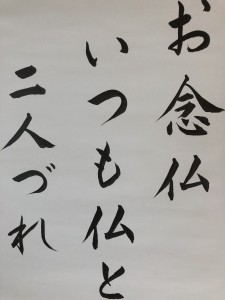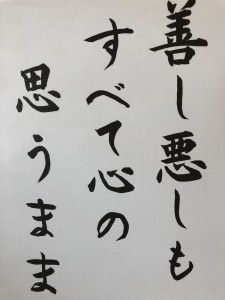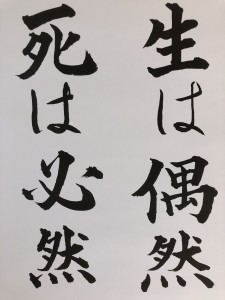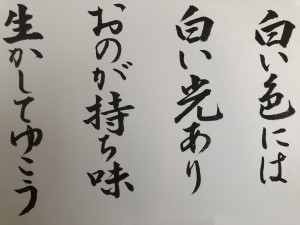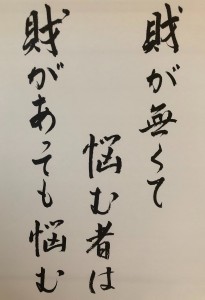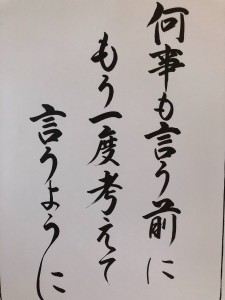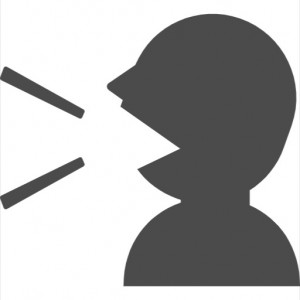Monthly Archives: 6月 2020
和尚のひとりごとNo254「法然上人御法語第二十三」
~ただ一向に念仏すべし~
【原文】
もろこし我が朝(ちょう)に、もろもろの智者達(ちしゃたち)の沙汰(さた)し申(もう)さるる、観念の念にもあらず。また学問をして、念の心をさとりて、申す念仏にもあらず。
ただ往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申して、疑いなく往生するぞと思い取りて申す外(ほか)には別(べつ)の仔細(しさい)候(そうら)わず。
ただし三心(さんじん)・四修(ししゅ)と申すことの候(そうろ)うは、皆(みな)決定(けつじょう)して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候うなり。
この外(ほか)に奥深きことを存(ぞん)ぜば、二尊(にそん)のあわれみに外れ、本願にもれ候うべし。
念仏を信(しん)ぜん人は、たとい一代(いちだい)の法をよくよく学(がく)すとも、一文不知(いちもんふち)の愚鈍(ぐどん)の身になして、尼(あま)入道(にゅうどう)の無智(むち)のともがらに同(おな)じうして、智者のふるまいをせずして、ただ一向(いっこう)に念仏すべし。
証(しょう)の為に両手印(りょうしゅいん)を以(もっ)てす。
浄土宗(じょうどしゅう)の安心(あんじん)・起行(きぎょう)、この一紙(いっし)に至極(しごく)せり。源空(げんくう)が所存(しょぞん)、此(こ)の外(ほか)に全く別義(べつぎ)を存(ぞん)ぜず。滅後(めつご)の邪義(じゃぎ)をふせがんがために所存を記し畢(おわ)んぬ。
建暦(けんりゃく)二年正月(しょうがつ)二十三日
大師在御判(だいしざいごはん)
【ことばの説明】
一枚起請文(いちまいきしょうもん)
起請文とは、自己の行動を遵守履行する旨を、神仏に対して誓った文のこと。平安末期に始まり南北朝時代以後盛んになった。この一枚起請文では、一枚の紙に念仏の教えの奥義を記して、その内容に一切間違いがないことが神仏の前に誓われている。
もろこし
「唐土」すなわち中国の古称。
観念の念(かんねんのねん)
観想の念仏とも言う。仏の相好(すがたかたち)や、仏国土(浄土)の様相を思い描くこと。浄土思想を説く経典の中では、比較的ポピュラーな修行法(観法)であったが、浄土宗では口で仏の御名を唱える口称念仏(称名念仏)こそが正義であるとしている。ただし所依の経論に含まれる世親菩薩の『往生論』に説く五念門(浄土門において要となる五つの実践法)には、第三に作願門と第四の観察門が明示され、これはそれぞれ禅定の止観を示す「奢摩他(しゃまた)」、「毘婆舎那(びばしゃな)」に当たるとされている。これはまさに仏の国土や阿弥陀仏自身、浄土の菩薩等の荘厳を思い浮かべることである。
三心(さんじん)・四修(ししゅ)
「三心」は念仏による往生を願う者が持つべき三つの心構え。至誠心(しじょうしん)・深心(じんしん)・回向発願心(えこうほつがんしん)のこと。総じて表現すれば、まことの心を持って、自身の至らなさと仏の引接(いんじょう)を深く信じ、全身全霊を持って浄土への往生を願う心。
「四修」とは往生を願う者が保つべき実践態度のことで、恭敬修(くぎょうしゅ)・無余修(むよしゅ)・無間修(むけんじゅ)・長時修(じょうじしゅ)の四。恭(うやまい)の態度を持ち、専ら阿弥陀仏とその浄土に関わる行を一生涯にわたって継続することを意味する。
二尊(にそん)
釈迦仏と阿弥陀仏のこと。釈迦仏(釈尊)は発遣の教主(はっけんのきょうしゅ)と呼ばれ、この世界(娑婆世界)の住人である私たちに対して、阿弥陀如来の浄土の存在を示しそこへ向かうように勧める役割を担い、阿弥陀仏は来迎の本尊(あるいは招喚教主 しょうかんきょうしゅ)と呼ばれ、実際に浄土願生者を迎えとるべく来る仏であるとされている。この事情を、善導大師は『観経疏』玄義分において「釈迦はこの方より発遣し、弥陀はすなわちかの国より来迎したまう」と記している。
尼(あま)入道(にゅうどう)
「入道」とは未だ正式の修行や学問を経ていない僧侶(僧侶の恰好をしていても実際には在家と変わりない存在)を指す。「尼」とは女性の出家者、もしくは女性の入道であると解釈される。
ここでは智者との対比において、智慧なく愚かな者たちを代表する存在として記されている。
安心(あんじん)・起行(きぎょう)
「安心」は詳しくは「安置」と「心念」のことで、本来は修業の成果として、心が散乱することなく安定し、信仰心が定まっている状態を指したが、浄土宗の立場では、凡夫の散乱心のままで、極楽往生を確信できること(決定往生 けつじょうおうじょう)を意味している。法然上人によれば「安心といふは心遣いのありさま」であり、上記の「三心」に他ならないとされる。
「起行」とは「安心」に基づく身的行為で、身・口・意の三業をもって阿弥陀仏の西方極楽浄土への往生の為に行う行為である「五念門(ごねんもん))、五種正行(ごしゅしょうぎょう)」を指す。これは世親の『往生論』に明示される、専ら阿弥陀仏とその浄土に関わる五つの実践方法のこと。
浄土宗では、浄土願生者の心構えと実践を「安心・起行・作業(さごう)」で総括するが、その「作業」とは上に述べた「四修」を指している。
邪義(じゃぎ)
教義本来の意味(もしくは宗祖の意図したところ)から離れた誤った解釈。
建暦(けんりゃく)二年正月(しょうがつ)二十三日
建暦二年は西暦1212年、法然上人が80歳の生涯を閉じられた二十五日の二日前に託されたのがこの一枚起請文であることから、この一枚起請文は元祖上人の御遺訓(ごゆいくん)として日々拝読されている。
【現代語訳】
(私のいうところの念仏は)中国や日本において、まことに数多くの智慧者・先達たちが議論を戦わせてきた(仏の御姿を心に念ずる)観想の念仏ではありません。また書物を通して学問を極めたうえで、念仏の意味を理解して称えるところの念仏でもありません。
ただ極楽浄土へ往生を遂げるためには、南無阿弥陀仏と唱えれば間違いなく往生できるのだと思い、心を定めて、称えるほかに特別の配慮も要りません。
ただし(往生を遂げるには)三心や四修と呼ばれる念仏者の在り方が求められますが、それらは皆「必ず南無阿弥陀仏によって往生するのだ」という気持ちを持つことの中で自ずと具わるものなのです。
もし私が今述べてきたこと以外に、さらに奥深い意味を心の中に秘めているとしたならば、(釈尊と弥陀の)二尊がお示し下さっている大慈悲を蒙ることができない、つまり彼の仏の(衆生救済の)本願から漏れ出てしまうことになるでしょう。
(かような)念仏をこころから信じようとする者は、仮に釈尊がその生涯をかけて説かれた教えの全てを悉く学びつくしたとしても、(自分をあたかも)文字の一つも知らない愚かな者であると受けとめて、尼や入道のような無知な者たちと同じであると見なして、智者のように振る舞うことなく、ただ実直に念仏をおこなうべきです。
以上、述べてきた内容に間違いがないことを両手印をもって証明いたします。
浄土の教えにおけるあるべきこころの在り方と実践(当為)は(いま記した)この一紙にすべて尽されています。
(私)源空の考えは、これ以外に特別なことは何一つありません。
私亡きあとに、本来の趣旨から外れた見解が出てくるのを恐れて、今思うところを記し終わりました。
時に建暦(けんりゃく)二年正月二十三日
源空 花押(法然上人の署名と印)
「起請(誓い)」であるとも、弟子たちへの「制誡(いさめ)」であるとも受け取られるこの一枚起請文は、朝な夕なに私たちのお勤めにおいて日常的に拝読される最も有名な御法語です。まさに建暦二年正月二三日当日、愛弟子の勢観房源智上人の請いに応えて著わされたとも伝承され、示寂の直前に記されたことからあたかも遺言の如く受け取られてきました。
その内容は元祖上人の考える「念仏」がいかなるものであるか、そのことを改めてはっきりと宣言され、それ以外に一切の秘め事がないことを明言されています。
釈尊はその生涯の最後に仰りました。
「何ものかを弟子に隠すような教師の握拳(にぎりこぶし)は、存在しない」
仏が示された教えに従い、「智者の振舞いをせず、あたかも愚者の如く、ただ一向に念仏すべきである」
元祖上人の御言葉をそのまま信受すること、それこそが私たち凡夫にとり、弥陀により来迎・引接という最大の救いの契機となることを改めて実感させてくれる御法語であります。
合掌
和尚のひとりごとNo249「凡夫」
私たちにもなじみ深い仏教語として「凡夫(ぼんぶ)」という表現があります。語感から「平凡な人、平均的な人」という意味かと思われるかも知れませんが、本来の意味は「仏教の理解が乏しく、修行実践もおぼつかない、凡庸で愚かな人」のことを指しています。
インドの原典に遡ってみればpṛthag-jana(プリタグジャナ)という言葉にたどり着きます。しばしば衆生や有情(心のある存在)と同じように使われるこの言葉は「異生(いしょう)」と訳されます。
「異生」とは、生来の煩悩に悩まされる私たちの在り様(ありよう)が、人それぞれであることを表わします。欲望の対象をいくら求めても満足出来ない人、生の悩みや苦しみ、あるいは死への恐怖から心の平安を失っている人…それぞれが異なった境遇にありながらも、煩悩に振り回され、迷いのただ中に生きていることに変わりはありません。
さて伝統的には覚りの智慧(仏智)を目指す修行者には、各々到達したレベルに応じた階梯(ステージ)が設定されていました。オーソドックスな考え方では、準備段階を入れた五段階の階梯があり、三つ目の「見道(けんどう)」以降が聖者(しょうじゃ)と呼ばれ、それに達していない修行者が凡夫(外凡 げぼん、内凡 ないぼん)とされていました。
ではその基準はどこにあったのかと言いますと、仏道修行の要(かなめ)であった「三昧(さんまい samādhi サマーディ)の上達具合によります。三昧とは「観法(かんぽう)」のこと、修行の過程においてさまざまな対象を観察し、その意味の理解を深めていく修行法です。
現在まで伝わっている伝承の中で、スリランカ・東南アジアに息づく南伝の伝統では、「諸行」すなわちこの世界の実相を観察するとされ、北伝の伝統では「四諦説(したいせつ)」を観察吟味していくこととされていました。 「四諦」とは仏教の開祖釈尊が菩提樹下で覚った内容とされ、またその最初の説法である初転法輪のときに説かれた際、かつての修行仲間の五比丘はただちに法眼(ほうげん)を得た(覚りを開いた)とも言われている、仏教において最も基本的な法門であります。生・老・病・死に代表される生きていく上での苦悩には、必ずその原因があり、また必ずその苦悩を滅する道があることを、自らの体験に即して語られたものです。
ところで私たちが奉ずる浄土の御教えにおいては、凡夫はどのように捉えられているのでしょうか?一言で言えば、私たち全員が凡夫であると考えます。凡夫とは上に見たように、未だ聖者の段階に達していない者、すなわち「無我」の道理を弁えず、「我=自分という存在」があり、この世の中が思い通りになって欲しいと願っている者のことです。
浄土教の祖師の一人である道綽禅師は、「安楽集」で末法における凡夫が救われる唯一の道として浄土往生の教えを明かし、法然上人が傾倒された善導大師は、「罪悪生死の凡夫(ざいあくしょうじのぼんぶ)」という表現で、今まさに末法に生きる私たちの在り様を示されました。
そこでは凡夫の意味は、末法という仏の教えが滅びゆく世界において、志はあっても仏道修行がままならない能力が劣った私たち自身のこととなります。そのような自らのあり方を真摯に見つめ、心の底から御仏の救いを求める私たちに釈尊が開示された道こそが浄土の御教えなのです。