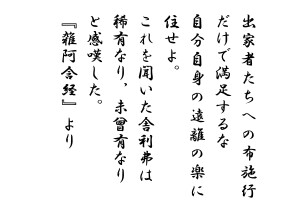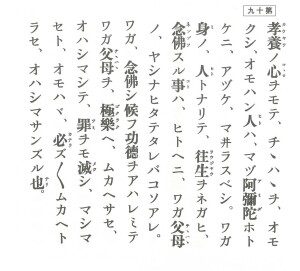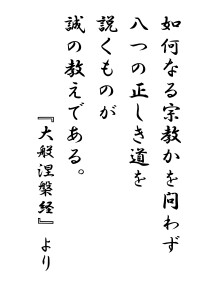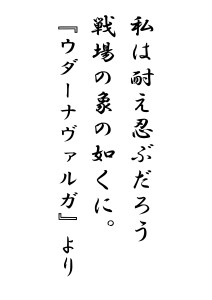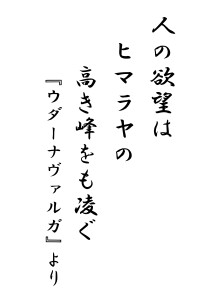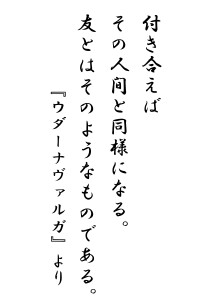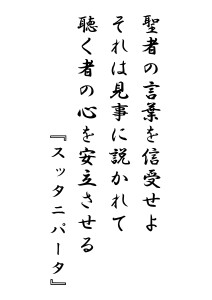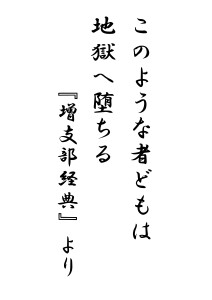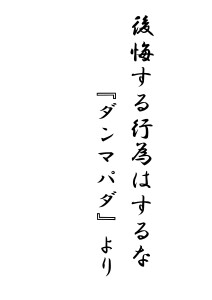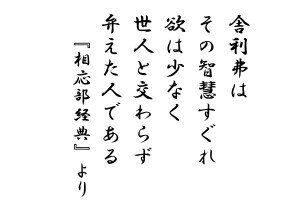和尚のひとりごとNo699「法然上人御法語後編第十九」
孝養父母(きょうようぶも) 示或人詞
【原文】
孝養(きょうよう)の心(こころ)をもて母(ちちはは)を重(おも)くし思(おも)わん人は、まず阿弥陀仏(あみだほとけ)に預け参(まい)らすべし。我が身(み)の、人となりて往生を願い、念仏する事は、偏(ひとえ)に我が父母の養い立てたればこそあれ。わが念仏し候(そうろ)う功徳(くどく)をあわれみて、わが父母を極楽へお迎えさせおわしまして、罪をも滅(めっ)しましませと思(おも)わば、必ず必ず迎え取らせおわしまさんずるなり。
孝養父母
親孝行。
【現代語訳】
両親に対する孝行の心をもって、父と母を大切に思う人は、阿弥陀仏にすべてお任せするべきです。私が人として生を受け成長でき、往生を願って念仏を申せるのも、ただ父母が私を育ててくれたが故有なのです。私が申す念仏の功徳をお喜び頂き、どうか父母を極楽へと迎えて、罪業を滅して下さいますように、そのように思うならば、仏が両親を迎え取って下さることは間違いありません。
世俗の恩愛を棄て悟りの境地へと進むこと、これが法然上人が勧める出世の孝養です。そして苦しみ多い世界から安楽なる西方浄土へ、自らのみならず父母をも迎え取って頂きたいと願うこと、これこそが未だ迷界にある私たちのできる最大の親孝行であります。