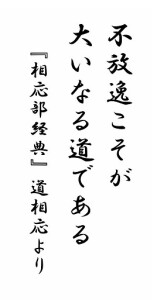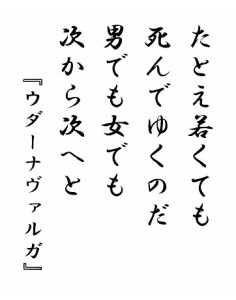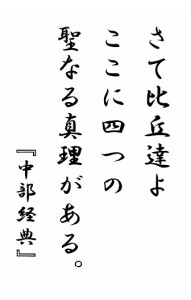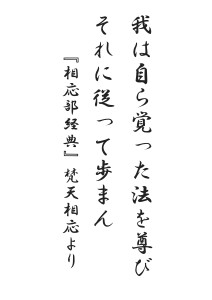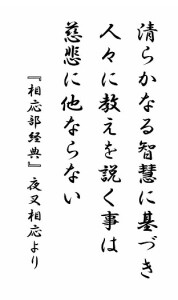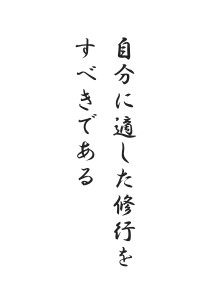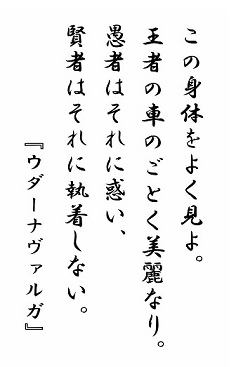和尚のひとりごと「五月五日は子供の日」
本日、五月五日は「子どもの日」として知られていますが、もともとは「端午の節句」と呼ばれていました。「端午(たんご)」とは月のはじめの午(うま)の日の事で、旧暦五月の最初の午(うま)の日に行われていた行事でした。ところで「午(うま)」の字は「ご」とも読める事から、五月五日になったと言われています。
さてこの「端午の節句」のそもそものいわれは、今から約2300年前、中国の楚(そ)の国王の側近であった屈原(くつげん)の故事にさかのぼります。人望もあり祖国を思う気持ちの強かった屈原でしたが、陰謀によりその地位を追われ失脚の憂き目にあいました。そして絶望の末に汨羅(べきら)という川に身を投げてしまいました。屈原を慕った人々は、屈原の死体が魚に食べられないようにと、小舟に乗り、太鼓を打って魚をおどし、さらに粽(ちまき)を投げ込んだといいます。
これが現在でも祝い事に欠かせないとされている粽の起源となります。また中国のボートレースであるドラゴンレースもここに由来するそうです。
その後も、毎年屈原の命日に供養祭を行い、厄難除けや無病息災を祈る行事へと発展していきました。
この行事が我が国に伝わったのは、盛んに大陸の文化を取り入れていた奈良時代のことで、5月の厄除けの行事として定着し、やがて武家社会の台頭とともに、勇壮なる男子の理想のイメージが込められてきます。五月人形を飾り、男子の健康を願う現在の「端午の節句」の原型です。
ところでこの季節に町を彩る鯉のぼりは、池や沼などでも生きていける生命力の強い魚として知られている鯉が、天高く昇っていく姿を表します。これは黄河の急流を登り切った鯉がついに竜となるという伝説に基づいています。『後漢書』に出る「登龍門(とうりゅうもん)」という言葉はここに由来しています。
また菖蒲湯に浴し、その厄除け・魔除けの効果にあやかろうとしたり、葉が落ちないと考えられた柏の葉に包んだ餅(柏餅)を食うことも、健康や無病息災を願う気持ちのあらわれでありました。
風にたなびく鯉のぼりの姿には、子供がすこやかに育ち、天高く駆けのぼるように立身出世を目指してほしい、今も昔も変わらぬ親の願いが込められているように思えてなりません。
和尚のひとりごと「伝道掲示板324」
田を耕すバーラドヴァーシャというバラモンが釈尊に言った。
「道の人よ。わたしは耕して種を播く。そのようにして生活の糧を得ている。
そなたも田を耕してから、食べたらどうだ」
釈尊は答えて仰った。
「バラモンよ、私もまた田を耕している。
信仰がその種であり、苦行が雨、智慧が軛(くびき)と鋤(すき)である。
慚(行為を恥じ入ること)が鋤棒(すきぼう)であり、心が縄である。
心を落ち着かせることが鋤先(すきさき)と鞭(むち)とである。
身を慎んで、言葉に気をつけ、節制して過食しない。
そして真実を守ることをもって、草を刈っている。
このようにして耕作を行い、それが甘露の実り(涅槃)をもたらし
あらゆる苦悩から解き放たれることにつながるのである。」
これを聴いたバーラドヴァーシャは
大きな青銅の鉢に乳粥(ちちがゆ)を盛り、捧げた。
しかし釈尊はそれを受け取らずに仰った。
「詩を唱えた報酬として得たものを食してはならない。
これが目覚めた人のならわしである。
その粥は青草の少ない場所か、あるいは生物のいない水中へでも沈めるがよかろう。」
水の中に投げ棄てられた粥は、あたかも熱した鉄製の鋤先を水につけた時のような音を発し、煙を出して沈んでいったという。
合掌
和尚のひとりごとNo566「立ち止まって深呼吸」
海の波の動きを「波動」と言います。風が強い日は波が荒くなりますが、全く風がなくても、たとえ水面に波が見えなくても、水面下では「うねり」となって波は必ず動いています。寄せては返す「波動」、1分間に17、8回あるそうです。私達の体で1分間に17、8回と言えば「呼吸」になります。安静時の健康な成人の平均的な呼吸数が「波動」とほぼ同じ数になるそうです。ですから釣りの好きな人が海に出て、釣り糸を垂れて横たわっていますと、一番心地良く休めるそうです。「呼吸」と「波動」が同じ数である故、心地良く感じるのです。呼吸数が18回として、その倍の36と言えば人間の「体温」になります。「体温」が36度でおおよそ、その倍の70となると「脈拍」。「脈拍」の倍の140と言えば「血圧」になります。「血圧」の倍の280は、胎児が母親の体内にいる日数になります。十月十日と一口に言いますが、この280日を100倍した28000日。これは「寿命」になります。天から授けて頂いたという事で「天命」とも言いますが、その「天命」が28000日。一年の日数、365日で割ってみると76点いくつになります。これがおおよそ、人としての「寿命」になります。有り難い事に今の日本人の平均寿命はこれ以上の方が多くなりましたが、大体70なかばあたりが良い頃合いの「寿命」です。一分間の「波動」が17、8回で人の「呼吸」と同じ。その倍が「体温」。「体温」の倍が「脈拍」。「脈拍」の倍が「血圧」。「血圧」の倍の280日が胎児が母親の体内にいる日数になり、その100倍の28000日が人の「寿命」になる。その様に考えますと、我々の日々の暮らしは大自然の法則の中で生かされているとも言えるのではないでしょうか。自分の力で生きているようだけれども、目に見えない力によって生かされている。生かして頂いているこの命と考えられるのです。目に見えない量り知れない不思議な力に対してお釈迦様は、「人智を超えた見えない存在があるのではなかろうか。」と手を合わせていかれました。肉体的にはご先祖様から頂いた血と肉でありますが、不思議な力によって今こうして生かして頂いている私達であります。
「ありがたし今日の一日(ひとひ)も我が命 めぐみたまえり天(あめ)と地(つち)と人と」
<佐々木信綱(のぶつな)1872~1963 国文学者・歌人>
晴れの日は、光の恵みを与えられ、雨の日は水の恵みが与えられます。そして大地には米や野菜といった農作物の恵みが出来上がります。食べる物に限らず日々の生活全て人や物に頼って生かされている私たちです。生きていく事は自分一人の力ではないと日々共々に感謝の気持ちで過ごして参りましょう。
和尚のひとりごと「伝道掲示板322」
初転法輪(しょてんぽうりん)において説かれた教えは中道の教えであり
四諦八正道(したいはっしょうどう)であったと伝えられる。
四諦(四つ聖なる真理)とは。苦諦(くたい)、集諦(じったい)、滅諦(めったい)、道諦(どうたい)の四つの真理である。
生きることは本質的には苦悩であり、その苦悩には煩悩という原因があり、
その煩悩を滅する事で苦悩が滅し、そのための道が八つの実践の道である事。
この教えを聴いたのち、かつて苦行をともにした5人のうちの一人、
コンダンニャ(憍陳如、きょうちんにょ)に法眼が開いたという。
法を見る眼、すなわち世の実相を理解する智慧が生じたコンダンニャは釈迦の最初の弟子となった。
現在に至るまで仏教の四大聖地に数えられる鹿野園(サールナート)での出来事である。
合掌
和尚のひとりごと「伝道掲示板319」
出家が守るべき戒律に最も精通していた事から「持律第一(じりつだいいち)」と
称せられた優波離(ウパーリ)に仰った言葉。
優波離は釈迦族の理髪師であり、当時のインドの身分制度(ヴァルナ)では
最下層のシュードラ(奴隷)の出身であったという。
優波離が出家を申し出たとき、釈尊はその出自に拘らずそれを許し、
また数ある志願者の中で、まず最初に彼を出家させたと伝えられる。
優波離はある時、阿蘭若(あらんにゃ、人里離れた山林や荒野)の行をしたいと師に申し出たが、
釈尊はたとえをもってこのように諭した。
”大きな象にとって楽し気な池での水浴も、
小さな人間にとっては恐ろしい体験となることもある。
そのようにそれぞれの身の丈にあった行を行うべきである。
そなたは衆中にて(ひとりではなく仲間とともに)修行を続けるように。”
合掌